
子どもに“お金の教育”なんて、まだ早いんじゃないの?

そんなことない!
実は、金融リテラシーの差は、大人になったときの生活力や経済的安定に大きく関係しています。
学校ではなかなか教えてくれない“お金の使い方”や“お金の考え方”を、家庭で自然に学ばせることが、これからの時代を生き抜く力になります。
この記事では、教育者目線で「子どもにお金を教える理由」と、「家庭で今すぐ始められる実践法」をわかりやすく紹介。
お小遣いの与え方・買い物ごっこ・貯金習慣のつけ方など、保護者が「今日からできる」 具体策をたっぷりお届けします。

🔹子どもに「お金の教育」が必要な理由

✅ お金の知識は生きる力になる
子どもにとって「お金」は、身近にありながらも、実はとても抽象的な存在です。
買い物で使ったり、お年玉でもらったりすることはあっても、「お金って何?」という本質に触れることはほとんどありません。
しかし、お金の価値・使い方・貯め方・増やし方を早いうちから学ぶことは、将来自立して生きていくための“生活力” を育てる重要な一歩です。
✅ 学校ではほとんど教えてくれない“金融教育”
日本では長らく「お金の話は家庭で」「お金の話は下品」とされ、学校教育でも明確に“お金の使い方” を教える場面は非常に少ないのが現実です。
📊「家計管理の教育を受けたことがある」人は、わずか16.3%(2022年調査)
つまり、大人になっても「収支のバランスが取れない」「ローンや借金で失敗する」 といった金銭トラブルの原因の多くは、子どもの頃に金融リテラシーを学ぶ機会がなかったことに起因しているのです。
✅ お金の知識が“人生の格差”を生む時代
現金を見ないまま取引をする時代に生きる子どもたち。
もしお金の教育が不十分なままだと…
- 無意識に浪費してしまう
- クレジットカードの仕組みを理解せず使ってしまう
- 借金の重みや金利の意味を知らない
こうした“金銭リテラシーの差” は、将来の進学・就職・生活水準に直結するといわれています。
✅ 早期教育が「習慣」をつくるカギ
脳科学の研究でも「習慣は早期に形成される」とされており、お金との健全な関わり方は、10歳頃までに基礎を育むのが理想的です。
基本的な金銭感覚を育てる親子会話の例
• 「お金は使えばなくなる」
• 「ほしい物を買うには貯める必要がある」
• 「人に与えることで感謝されることもある」
🔍統計データ
- 金融広報中央委員会(2022年):「金融教育を受けた経験がある若者は16.3%にとどまる」
- OECD国際調査(PISA2018):「日本の15歳の金融リテラシー平均は、OECD加盟国平均を下回る」
🔹家庭でできる!お金の教育3つの実践方法

「金融教育」と聞くと難しそうに感じますが、実は家庭の中で楽しく・自然にできる方法がたくさんあります。
ここでは、子どもの年齢や理解度に合わせて実践できる、代表的な3つのアプローチをご紹介します。
✅ ①「お小遣い」は“与え方”が教育になる
お金の教育において、お小遣いは最大の教材になります。
ただし、「ただ毎月渡す」だけでは、学びにはつながりません。
📌教育効果を高めるお小遣いの工夫例
• 目的別に使い道を話し合う:「これは貯金、これは使う用」など分類させる
• 毎月“定額制” で与える:計画的に使う習慣がつきやすい
• 帳簿(記録)を一緒につける:何に使ったか、どう感じたかを振り返る
• “働いて得る”経験をさせる:簡単なお手伝いに報酬をつけて、労働=対価の理解を促す
✅ ②買い物ごっこで“疑似体験”を積む
小さい子どもには、「買い物ごっこ」や「お金のおもちゃ」を使ったロールプレイ(疑似体験) が有効です。
📌実際のやり方
• 値札を自分でつけさせる:「高い」「安い」の基準が自然に身につく
• 紙のお金で支払う&おつりを計算する:数の感覚+交換の理解
• レシート風の紙を発行する:本格的に遊べて学びも深まる
✅ ③日常会話で“お金の話”をタブーにしない
日本では「お金の話はタブー」とされがちですが、家庭内の会話に自然と“お金” の話題を混ぜることが教育の第一歩です。
📌話題に取り入れたいテーマ例
• 「今月の食費は〇円だったね。何に一番かかったかな?」
• 「このゲーム、5000円するけど、本当に必要かな?」
• 「欲しいものがあるなら、どうやってお金を貯める?」
🔹すぐに始められる!実践のポイント
✅ 年齢別に考える「お金教育」の第一歩
幼児期(3〜6歳)
• 買い物ごっこで「お金=モノと交換する手段」を遊びながら学ぶ
• 親が「〇〇を買うのに〇〇円かかったよ」と口に出す
小学生(7〜12歳)
• 毎月のお小遣いの使い方を記録させる
• 欲しい物を「買う vs 貯める」で比較させる
中学生以降
• 家計の一部を一緒に考える
• アルバイトや投資ゲームで“自分のお金”を体験
✅ 習慣化するための3つのコツ
- ノートやアプリで記録をつける
- 毎週5分だけ“お金の話をする時間”を作る
- 失敗を責めずに「一緒に考える」対話を重視する
✅ おすすめの本・アプリ・ツール
📚 書籍:
• 『子どもにお金の教育をしよう!』(山崎元)
• 『おかねってなあに?』(絵本)
📱 アプリ:
• まねぶー(子ども用お小遣い帳)
• おかねのけいさんゲーム(支払いやおつりの練習)
🔹実際の成功事例・失敗事例
「実際にお金の教育をしたらどうなったのか?」
これは多くの保護者が気になるポイントです。
ここでは、実際の家庭での成功事例・失敗例を紹介しながら、教育者としてのアドバイスも加えて、読者が参考にしやすい形で解説します。
✅ 成功事例①:買い物体験が“考える力”を育てた
小学4年生・女の子の保護者
「おもちゃを買いたいと言うので、月のお小遣いを貯めて購入させました。
一度買ってみて“思ったより遊ばなかった”と本人が反省。次からは“本当に欲しいか”を自分で吟味するようになりました」

うちの子にも、こういう経験をさせてみたいな…

体験から学ぶ“判断力”が自然と育っていますね
👉 ポイント解説:
このような経験を通して、「欲望に流されず選ぶ」「お金を使う前に考える」 といった力が自然と育ちます。大人の価値観を押しつけず、子どもが体験を通じて学ぶことが重要です。
✅ 成功事例②:兄妹で“貯め方”に差が出た!
小学6年の兄と小学2年の妹の家庭
「同じ額を渡しても、兄はすぐ使い切ってしまい、妹は少しずつ貯めるタイプ。
家族で“どうやって使ったか”を話し合うようにしたら、兄も少しずつ意識するようになりました」
👉 ポイント解説:
お金の使い方には個性が出ますが、兄妹間での比較ではなく、「なぜその使い方をしたのか」を対話することで気づきが生まれます。
✅ 失敗事例①:報酬ばかりで“金銭優先”に
「お手伝い=お金をもらえる」と教えすぎた結果、子どもが「それ、いくらくれるの?」と聞くように…。
誰かのために行動する気持ちが薄れてしまったようで、少し後悔しています。
👉 教育者の視点:
「行動のすべてに報酬がつく」という考え方は、利己的な金銭観を育ててしまう恐れがあります。
お金の報酬と感謝・喜びといった「内面的な報酬」をバランスよく伝えることが大切です。
✅ 教育者の視点:成功する家庭の共通点
筆者が教育の現場で感じる、お金の教育がうまくいく家庭には共通点があります。
📌成功家庭の特徴
• 話し合いを大切にしている
→ 「どれが高い?」「買うとしたらどれを選ぶ?」など、日常の選択を一緒に考える家庭は、子どもの金銭感覚も育ちやすい。
• 親自身が学ぶ姿を見せている
→ 「お父さんも最近この本を読んでてね」と話すだけで、子どもは“学ぶ姿勢”を自然と受け取る。
• 正解を教えるより一緒に考えるスタンス
→ 「それはダメ」と頭ごなしに否定するのではなく、「どう思う?」「他に選び方あるかな?」と問いかける方が、主体的な思考を促します。
🔹まとめ&次のステップ
✅ この記事の要点まとめ
ここまでご覧いただき、ありがとうございました。
改めて、子どものお金教育において大切なポイントを整理しておきましょう。
✔️ なぜ子どもに金融教育が必要なのか?
→ 社会の仕組みが複雑になる中で、「自分で考え、お金を管理する力」は“生きる力”の土台になる。
✔️ 家庭での工夫がすべての土台に
→ お小遣い、買い物ごっこ、日常会話など、家庭での体験が金融リテラシーの芽を育てる。
✔️ 失敗も成功も、学びのチャンス
→ 子どもは“やってみて”成長する。使い方を失敗しても、それが一番の教育になる。
✔️ 親子で一緒に学ぶ姿勢がカギ
→ 教える側が「一緒に考える姿勢」を持つことが、子どもにとっての信頼と安心に。
✅ 今日からできるアクションリスト
✔️ お小遣いの渡し方を“話し合い型”に変えてみる
✔️ 買い物ごっこやお店屋さんごっこを週末に楽しんでみる
✔️ 毎週末に「お金について話す時間」を5分だけ作ってみる
✔️ 子ども向けの金融教育絵本を読み聞かせしてみる
✔️ アプリで簡単な記録をつける習慣を一緒に始めてみる
🔹よくある質問(Q&A)
✅ Q1:お金の教育って、何歳から始めればいいの?
A:3歳頃から“体験ベース”で始めるのが理想です。
「買い物ごっこ」「お金のやりとり」など、遊びを通して“交換”や“価値”を意識させましょう。
✅ Q2:お小遣いの金額やルールはどう決めたらいい?
A:子どもの年齢・生活環境・価値観によって柔軟に決めましょう。
学年×100円が目安とも言われますが、金額よりも「どう使ったか」を振り返る対話の方が大切です。
✅ Q3:親の私自身が、金融知識に自信がありません…
A:一緒に“学ぶ姿勢”を見せるだけで十分です。
絵本やアプリ、家計の話題を通して、自然に学び合う関係を築くことが一番の教育になります。
✅ Q4:子どもが全然興味を示しません。どうしたらいい?
A:押しつけず、生活の中に“楽しみ”として取り入れましょう。
ゲームや目標チャレンジを通じて、成功体験を積ませることで、自然と意欲が湧いてきます。
🔹今後の金融教育に向けて|読者へのメッセージ
お金の話は難しくありません。むしろ子どもたちは「お金」に強い好奇心 を持っています。
だからこそ、タブー視せずにオープンに、楽しく学ぶ環境をつくることが重要です。
本記事で紹介した内容は、どれも今日から家庭で始められるものばかり。金融教育=難しいというイメージを変え、子どもが自分で人生を切り開く力を育てる第一歩を、ぜひあなたのご家庭でも踏み出してみてください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/447abf75.a5cbb265.447abf76.749ea16f/?me_id=1213310&item_id=20838399&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3720%2F9784827213720_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46ce7240.2a7aaf5a.46ce7241.31ede763/?me_id=1404937&item_id=10002117&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fboardgame-album%2Fcabinet%2F09580404%2Fkodomo-okane-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/447abf75.a5cbb265.447abf76.749ea16f/?me_id=1213310&item_id=21515654&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7868%2F9784801207868_1_11.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
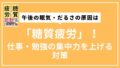
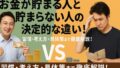
コメント